特集 地域総合防災力の強化~消防と住民が連携した活動の重要性~
1 地域総合防災力の強化の必要性
(1)切迫する大規模災害
我が国では平成20年度も、岩手・宮城内陸地震や相次ぐ水害など、全国各地で大規模な自然災害による被害が発生している。
集中豪雨が頻発していることや、東海地震、東南海・南海地震、首都直下地震等の大規模地震の発生の切迫性が指摘されていることもあり、国民の安心・安全に寄せる関心は極めて高い。
消防防災体制の充実強化は、国、地方を通じた最重要課題の一つである。

(2)地域総合防災力の強化
大規模な災害に対処するためには、常備消防(消防本部・消防署)の広域化や被災地への応援部隊として全国から出動する緊急消防援助隊の充実など広域的な体制の整備も大切であるが、同時に、発災直後の速やかな対応を図るためにも、自助・共助の精神に基づいた各地域の防災体制を強化していく必要がある。
地域の防災を支える担い手は様々である。消防機関はもちろんのこと、自治会や町内会等を単位とした住民の自主防災組織や婦人(女性)防火クラブなど民間の防災組織、さらには企業その他の団体やボランティアグループ、一般の住民なども、地域防災の担い手である。
こうした担い手が互いに連携するとともに、平時の予防活動から応急対策、そして復旧に至るまでのあらゆる活動が円滑に行われなければならない。
いわば地域の総合的な防災力(この特集において「地域総合防災力」とする。)の強化が急務となっているのである。
また、大規模な災害に限らず、例えば依然高水準にある住宅火災の被害を軽減していくためにも、地域全体での取組は欠かせない。住民一人ひとりが火災の予防に努めることや、ひとたび火災が発生すれば消防機関が迅速に出動し、消火にあたることはもちろんであるが、普段の防火意識の普及啓発活動や住宅用火災警報器の設置などの住宅防火対策の面では、常備消防や消防団が、婦人(女性)防火クラブなどの民間組織や地域住民と連携・協力することが必要である。
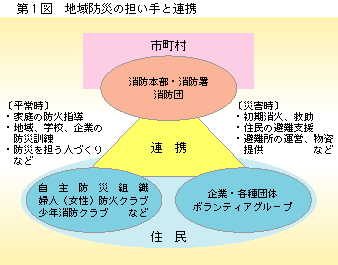
(3)地域総合防災力の充実方策に関する小委員会報告
消防審議会に設置された地域総合防災力の充実方策に関する小委員会において、平成20年11月に報告書が取りまとめられた。その要点としては、まず地域防災を担う人づくりの必要性が挙げられる。地域の防災を支えるのは、住民が自ら判断し、また互いに助け合って行動する自助・共助の取組である。消防庁では、eラーニング方式による教育システム(防災・危機管理eカレッジ)を構築し、子どもを含む住民等を対象に基礎的知識から実践的な内容まで様々なコンテンツを提供しているところであるが、今後は、広く住民が防災に関する知識や技術を習得する機会をさらに増やしていくとともに、地域のリーダー役となる人材の育成により一層力を入れていく必要がある。
そのほか、地域防災の要となる消防団の充実強化や民間防災組織の活動促進等が掲げられており、これらの点に関して、以下(2及び3)に述べる。
